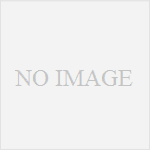沙耶と匠は、紅葉を堪能しようと車を山道へ進めていた。
山の入り口はまだまだだったが、奥に進むにつれ木々の葉が黄色や赤に色づいていた。
「おー。いーねー。テレビで見たことある感じ。もしかしたら生で紅葉した山ごと見るの初かもー!」
「えー!そーなの?ちょっと不憫に見えたよー。笑」
「おいおい。哀れまれた?まじかぁー。笑」
父親は忙しい人だったし、母親の運転でクネクネ山道なんて、親子心中のドライブになる。
色づいた木々なんて、せいぜい街路樹のイチョウくらいしか実際に見たことはなかった。
匠は窓を開けて年甲斐もなくはしゃいでいた。
沙耶はそれを見て「ふっ」と笑った。
「もう少し行くと、道の駅みたいのがあるよ。ちょっと寄っていー?」
「おう!寄ろう寄ろう!疲れただろ?休憩したら俺運転代わろっか?」
「大丈夫大丈夫!あ 見えたよ。入るね!」
道の駅は、すごく大きいわけでは無いがなかなか風情のある平家の建物と、しっかり駐車場が確保されていて、たくさんの人たちが訪れていた。
駐車場の奥にはすっかり秋の色に染まった山を一望できる場所が、歩道の先にあった。
沙耶はお手洗いに行った後、なんとなく一人でふらっとここに足が向いた。
「はぁーっ。」空気が綺麗できもちぃい。
「ちょっと……寒ぃな。」「寒ぃね。」
最後の言葉がシンクロしたと思ったら、背中と木の柵にもたれていた手があったかくなった。
匠が後ろから抱き締めるようにして、沙耶の手の上に手を重ねた。
「あったかい?」
「……うん。」
すっぽりと匠の中に収まってしまうだけに、まさに極暖。
「沙耶……俺も あったかい。」
「マ マ。あったかぃ……。」
ヒロっ!
沙耶の脳裏に最期のヒロが浮かんで、一瞬にして極暖から背中を蹴られて一面氷の世界に滑り込んだように、身体がぶるっと震えた。
「どーした?」
匠は沙耶に驚いて見つめてくる。
「ご ごめん。なんでもない。大丈夫。」
そう言うが、明らかに唇の血の気がなくなり早足で車に向かう沙耶を心配そうに見ていた。
「……ヒロ。」
匠から逃げるように車に向かった沙耶は、匠がすぐさま追って来ない事にホッとした。
「だめ。今日の目的を果たさなきゃ。泣いてる場合じゃない。」
頬をパチンと叩いて、シャンとしろと自分に言い聞かせた。
コンコン。匠が車のボンネットにノックして、寄りかかる。
「沙耶、あったかぃの買ってきた。飲もっ。」
匠が何事もなかったように、穏やかな笑顔でミルクティーを自分の顔の横でアピールしている。
「ふっ。」その可愛いさに、少しこわばってしまったが、なんとか笑い返した。
ブォンブォン パッパー。
やかましい音と、数のバイクが入ってきて、みるみる駐車場の、いや、道の駅は全体を穏やかな雰囲気を壊した。
来た。
ここは、こういう集団が毎週末集まってくる。
沙耶はこれを待っていた。
静かで穏やかだったこの場所の雰囲気が、ガラッと変わった。
水槽の中に網を入れた時の魚みたいに、皆忙しなく集団を避けて散った。
ブォンブォンブォンブォン。ボボボボボ……。
匠から笑顔が消えた。
懸命に平静を装うとしているのがわかる。
沙耶はまだその時じゃない……そう自分に言い聞かせて匠の様子に気が付かないフリをしていた。
「つっー。」頭を抱える。
沙耶はその様子を横目で冷たく伺う。
何か思いだして!些細な事でもとりあえずいいから。
匠の顔がどんどん青白くなって行くのがわかった。
沙耶にそれを、悟られないようにと必死に隠しているのもよくわかった。
呼吸が速くなっている。
「はぁはぁはぁっ。うっー。」時々こめかみを抱えてうなる。
もう隠せないと思ったのか辛そうに顔を歪めて沙耶を見る。
その表情(顔)でみないで。喉の奥に、泣くのを我慢するときのあの鈍い痛みを感じた。
その潤んだ目、力なく手を伸ばす匠を思わず抱き寄せそうになる……でもそんなこと、沙耶には許されない。
匠と同じように、いや、匠よりも顔を歪めながら声にだせない叫びを唱えた。
思い出して早く!お願いだから。少しでもいいから。ヒロを。
いつの間にか涙が出ていた。何でこんなに辛いんだろ。
自分が苦しいよりキツい。
好き……だから。そんなの分かってる。そんな表情(顔)見せないでってば。
ついに、沙耶は匠の両耳を塞いだ。そして目を見て優しく微笑んで言った。「大丈夫。大丈夫。」
耳を塞いだから匠は聞こえないが、その口の動きと、沙耶の柔らかな表情で分かった匠は苦しいながらも、ふっと力なく笑った。
匠は沙耶の腕の中にしっかり抱かれて、呼吸を落ち着かせた。
沙耶は微笑んで泣いていた。匠の肩に雫が落ちた。