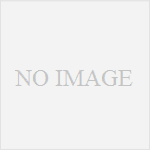深夜1時。匠の携帯に病院から電話。
「まじかー。この時間の電話は緊急事態しかないよな、」
「もしもし。」
「すみません。こんな時間だから迷ったんですが。」
「ん?どーした?」
「…雄也くんが、先程」
雄也…そう。工事現場事故で眠り続けている少年だ。
「息をひきとりました。」
匠の手から携帯が滑り落ちて、床で大きな音を立てた。
彼は、額縁の中で元気に笑っていた。
「こんなふうに笑ってたんだな。」
匠は初めて見る彼の笑顔に、目を細めた。
また笑える日を、きっと信じて今まで頑張って来たに違いない。
悔しくてたまらなかった。自分の無力さが、虚しくてたまらなかった。
「先生、わざわざお越し頂いたんですね。ありがとうございます。」
雄也の母だ。
匠は喉が締め付けられるような感覚の中、なんとか声を振り絞って言葉をかけた。
「助けてあげられなくて、本当に申し訳ありません。」
「…。」
母親はしばらくの沈黙の後、静かに口を開いた。
「先生には本当にお世話になりました。ありがとうございました。」
「でもね、本当に勝手だし、お門違いなのもわかってるんだけど…。やっぱり、先生を少し憎んでしまうんです。」
「ごめんなさい。頭ではわかってるんです。だけど、心がどうしても…誰かのせいにしたいんです。きっと。」
「ごめんなさい。」
子を失った親の気持ちを、医者としてたくさん見てきた分、わかるような錯覚をしていた。
沙耶のお腹に宿った小さな命を失った今、それは本当に錯覚でしかなかったことに気づいた。
親はいつも子を想い、子もそれを全力て受け止める。
いくら投げても受け止める子を失った愛情は、暴走してそこから虚しく外れて、匠を攻撃した。
匠は深く頭を下げて、そこを去った。
堪えていた涙と、悔しさがこみ上げた。
と、同時に…自分がおそらくしてしまっただろう事、忘れた信じたくない自分の過ちの罪の重さに押し潰されそうだった。
『俺は、誰かの…誰かのかけがえない子供を殺めたんだ。』
また激しく頭痛に襲われながら、フラフラと勝手に足は向かっていた。
ピンポーン。
匠はドアを開ける沙耶に泣きながら抱きついてガタガタと震えた。
「大丈夫?じゃないよね。」
沙耶はあの少年を助けたくて必死だった匠を知っているから、心情を察して慰めようとした。
「あの子も良く頑張ったんだよ。もう…痛くないし、きっと楽になって…」
「違うんだ。」
「え?」
匠が力ない眼で沙耶を見て、すぐそらす。
「何?」
「俺は…人殺しなんだ。しかも、、、子供を。」
沙耶は匠をじっと見て、ただ黙った。
『思いだした…んだね。』