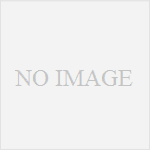「あーなんか寒気がするんだよなー。」
「匠大丈夫?顔赤いよ?」
杏は匠の顔を覗き込んで、ほっぺたを触った。
「ほら!熱いよ。絶対熱あるって!」
そう言いながら、今度は両手で匠のほっぺたを触ってグッと顔を引き寄せ、自分のおでこで熱を計る。
匠は熱でボーッとしながらも、頭に沙耶の顔が浮かんで慌てて杏のおでこから逃れた。
「何なの?急に慌てて。いつもの事でしょ?」
「いや……あの、さ いつもの事って。一応男と女なんだし。」
「ん?何いまさら。」
杏はぶっきらぼうに言い放って、去っていった。
何故かすごい早足で。
もう!なんか、意識されるとこっちまでなんか、恥ずかしくなる。
杏は熱もないのに顔を赤らめて、自分の部屋に帰っていた。
「なんであいつと幼なじみなんだろ!かっこよすぎちゃって他の人が目に入らない。」
杏がこの気持ちに気がついたのは、いつだった?
割といつも近くにいたし、それが当たり前だと思っていた。
それが、匠に彼女ができた時、いつものポジションに自分がいない。当たり前と思っていた『そこ』が決して当たり前じゃない場所だったことに気づいた。
恋人と言う存在がない時には、そこに居座れる。
いつかは、恋人として匠の『そこ』にいたいのだが、その想いを口に出して今の関係が終わってしまうのが怖い。
「こんないー女、そう滅多にいないんですけどー!」
自分で言っても……むなしいだけだな。
最近匠はなんか浮かれてるし。
杏は「はぁーっ。」と大きくため息をついた。
ピピピピッ。
体温計はやっぱり何度みても平熱ではない……つまり発熱を表示している。
「あーぁ。38.1度。先生、こりゃアウトですな。
ここの平和のために、大人しく帰ってください。」
「ほら。早く早く。」
ここのところ、あの少年の病室通いでほぼ毎日1時間くらいの仮眠だったことが祟ってか、匠の身体は本能的に休めと熱を出したようだ。
「すんません。じゃー帰らせてもらいます。」
「あー。もー。情けないっ。」
頭の中でガンガン鐘を鳴されてる感じと、耳に響く嫌ーなエコーに耳を塞いだ。
ピコン
ベッドの隅の匠の携帯がLINEの通知をする。
ますます熱が上がったのか、頭から湯気が出そうな程火照っている。
「やばいなー。」
意識が朦朧とする中、反射的に携帯を持ったが見る余裕はなく胸の上で握りしめていた。
ブブブブブブ
沙耶はなんとなく気になって、匠に電話していた。
匠の胸の上で携帯が振動して、匠はハッとして電話に出た。
熱と、今の振動でびっくりしたので電話に出た匠の呼吸の速さは、今度は沙耶を驚かせた。
「はぁはぁはぁはぁ……。」
「え?どうしたの?大丈夫?」
沙耶はただ事ではないと、部屋着にメガネのまま部屋を飛び出して匠の部屋に向かっていた。
ピンポーン
返事がない。
ピンポーン。ピンポーン。
「何があった?」
ピンポーン。ピンポンピンッ
ガチャ
ドアが少し開いたその隙間から茹タコのような真っ赤な顔した匠が見えたかと思ったら、みるみるうちに沙耶に向かって倒れ込んで来た。
「わぁーっ。」
沙耶は慌てて匠を受け止めたが、完全に脱力した匠の重さに耐えきれず、危うく共倒れしそうになった瞬間、匠が閉まったドアに手をつき、なんとか持ち堪えた。
ドアと匠の間でいわゆる壁ドンされた沙耶は、胸キュンするのも忘れて匠のおでこを触った。
「なにこの熱!」
沙耶は匠の脇を抱えて、よろつきながら何とかベッドへ連れて行った。
「弱りきってるね。」額の汗をぬぐいながら沙耶がそう言うと、匠はうっすらと目を開けて、フッと笑った。
「冷たくてきもちぃー。」
沙耶の手を自分の顔に押し当てて、安心したかのようにスーっと寝息を立てた。
沙耶はしばらくそのままに様子を見て、眠りが深くなってから手を離した。
「ふーっ。さて、氷はあるのかな?」
とりあえず、病人は看病するしかない。
手首の怪我の時の借りを返すだけよ。
沙耶は自分に言い訳をしながら、買ってきた氷枕の準備をしながら、いつの間にかヒロとの思い出の旅に出ていた。
「んー。ここ痛いっ……。」
インフルエンザが流行る冬。
ヒロはおでこを押さえながらずっとそう言っていた。
でも、絶対に泣かなかった。
ヒロはとても我慢強い子だった。
こんなに小さくても、母が悲しくなるのを感じてどんな時も決して涙をみせなかった。
辛いときこそ、逆にヒロは笑った。
だから、沙耶もいつも笑顔でいるように頑張った。
でも、一度だけ……一度だけ沙耶はヒロの前で泣いた。
母が死んだ時だった。
いつもの様に、笑顔を見せたのに目からは涙がこぼれていたらしい。
それを見たヒロが言った。
「ママの真似っこする。」「今だけ、泣いてもいい?」
そう言ってヒロは泣いた。
沙耶は母を、ヒロは大好きなばぁばを失った。
その日だけは
ふたりで声をあげて泣いた。
「沙耶?」
解熱剤が効いたのか、茹でたこじゃなくなった顔を戸の隙間から覗かせた。
沙耶は慌てて涙をぬぐって振り向いた。
「どう?少しは身体、楽になった?」
匠は沙耶の顔をじっと見つめて、
「おいで。」と穏やかな声で言った。
沙耶は、その声に引き寄せられるように、自分でも驚くくらい素直に匠の胸にうもれた。
涙が溢れて止まらなかった。
匠はただ、黙って沙耶を優しく包み込んだ。
誰かに寄りかかるのは……いつぶりだろう。